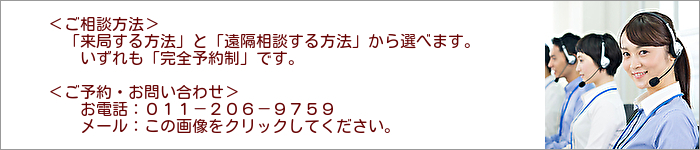手足の冷えがつらくて眠れない!つらい冷え症を漢方で解決しませんか?
毎年冬になると、布団に入っても手足が温まらず寝付けないとか、部屋に暖房を入れていても手足が冷たくてつらいといったお悩みはありませんか?
冷え症は女性特有の症状と思われがちですが、近年は男性でも冷え症に悩まされている人が増えてきました。
今回は冷え症につながる原因や東洋医学からみた寒い冬の養生法、冷え症に対する漢方薬のアプローチなどを解説いたします。ぜひ最後までご覧になって下さい。
つらい手足の冷えを解消するヒントにしていただけるとうれしいです。
冷え症につながる原因
冬は外出したときなど誰でも手足が冷えることはありますが、室内に戻っても冷えの改善が見られない場合は「冷え症」になっている可能性が高いです。
冷え症は体温調節機能がうまく働かないため引き起こされます。
主な原因は生活習慣によるもので、よくみられるものには次の6つが挙げられます。
- 自律神経の乱れ
寝不足や日常生活でストレスがたまり、体の機能を保つ自律神経のバランスが崩れると、体温を調節する指示が行き届かなかったり、末梢血管の収縮が続いて血流の悪い状態が続いたりします。
- 皮膚感覚の低下
下着やタイトな洋服によって体が締め付けられると血行が悪くなり、暑さや寒さを感じる皮膚神経の働きが弱まってしまいます。
また1年中エアコンで部屋の温度を同じに保っていることも、温度を感じる皮膚神経の働きがにぶる原因となります。
- 血行不良
低血圧や貧血がある人は、全身に血液がきちんと行きわたらず、冷えを感じやすくなります。
- 筋肉量が少ない
筋肉は動かして熱を産生する働きと、血液を巡らせるポンプのような働きがあります。
筋肉量が少ないと熱があまり作られず、血液を送り出す力も弱くなります。
- 女性ホルモンの影響
女性は月経周期にともなってホルモンバランスに変化があり、それがストレスとなって自律神経の働きにも影響をおよぼして、血流が悪くなることがあります。
- 食生活の乱れ
冷たい飲み物や食べ物を日常的に摂っていると、体が内側から冷え切ってしまい、内臓を温めるために血液が体幹に集まってしまうため、手足の血流は悪くなります。
東洋医学と西洋医学、冷え症のとらえ方の違い
手足や体の冷えでつらい体質のことを、東洋医学では「冷え症」と表記するのに対して、西洋医学では「冷え性」と表記します。使われている文字が違う理由に、冷えに対するとらえ方があります。
西洋医学では、冷えの背景に貧血・低血圧・甲状腺機能低下症など明らかな異常がみられる場合には治療が行われますが、検査で異常がなくはっきりした原因がない場合は冷える体質・性質の「冷え性」として扱われます。
病的な原因が見られない冷えの場合、特に治療は行われません。
東洋医学の場合、冷えは「万病のもと」と言われるように、さまざまな病気につながる原因として重要視しているため、冷えの症状に対する治療が必要と考えられています。
治療を行うときには、熱を作れないのか熱を全身に送り出せないのかなど体質や原因を見極めて、症状にあった漢方薬を処方し、さらに食事など養生法の指導もします。
冷え症は早めの手当てが必要
冷え症は病気ではないから問題ないだろうと軽く見てしまいますが、放っておくとさまざまな悪影響があります。
冷え症が元となって引き起こされる病気や、東洋医学における冬の過ごし方と冷え対策について解説いたします。
冷え症の放置で起こる病気
手足の冷えが長く続いて体温が低い状態におちいると、免疫力や全身の代謝機能にも影響が出て、次のような病気につながることがあります。
- 血液の流れが悪くなることによる肩こり・月経痛
- 自律神経の働きが低下することによる不眠・頭痛・うつ症状
- 免疫力が低下することによる風邪・インフルエンザ等の感染症
- 代謝機能が落ちることによる肥満・抜毛・皮膚乾燥
冷え症を甘く見ず、重篤な病気を引き起こす前に手当てをしていきましょう。
東洋医学からみた寒い冬の過ごし方と冷え対策
暦では11月上旬の立冬から2月の上旬の立春までが「冬」です。
東洋医学の考え方で「冬」は動物が冬眠するのと同じように、寒さから身を守り気(エネルギー)を蓄えて春に備える季節とされています。
冬の過ごし方について、中国最古の医学書「黄帝内経」には次のように書かれています。
- 冬は穏やかな気持ちで過ごす
- 夜は早く寝て、朝は日の出を待ってゆっくり起床する
- 寒さを避けて、体を温かく保ち、汗をかくような行為は控える
自然の法則にしたがって、冬は静かに過ごし体を温めて寒さから守ることが大切です。
体を効率よく温めるにはお腹や腰まわりを保護するようにします。
腹巻を使ったり、湯たんぽをお腹や腰にあてたりして温活に努めましょう。
また冬は寒さと冷えにより五臓の「腎」が傷つきやすい季節と言われています。
腎は生命力や泌尿器系と関わりが深く、不調を起こすと足腰の冷え・むくみ・頻尿・月経異常・性欲低下・白髪が増えるなどの症状が現れます。
そのため冬の食生活では、体を内側から温める食材や「腎」を補う食材を摂るように心がけると良いでしょう。
具体的な食材は次の通りです。
- 体を温める性質のある食材
羊肉・鶏肉・もち米・ナツメ・かぼちゃ・にんにく・にら・玉ねぎ・生姜など
- 腎を補う性質のある食材
黒豆・小豆・黒ゴマ・やまいも・黒糖・ひじきなど
冷え症の漢方薬での治し方
冷え症は放置しないことが大切で、先ほど解説した冬の過ごし方や対策を行いつつ、漢方薬の力を借りて早めに症状を楽にしましょう。
手足の冷えで眠れないほど症状が進行している場合は、養生に加えて漢方薬治療が必要になるケースが多いです。
冷え症でよくみられる証(東洋医学からみた体質)と漢方薬での治し方についてみていきましょう。
- 脾胃両虚
五臓六腑のうち脾と胃の働きが弱く、食事を消化して熱を生み出す力が低下している状態です。
お腹が冷えるのが特徴で、軟便・下痢・食欲不振なども伴います。治療は脾と胃を補う漢方薬を用います。
- 瘀血
血行が悪く全身のすみずみまで血が巡らない状態です。
手足の冷えやしびれが出るのが特徴で、肩こり・頭痛・冷えのぼせ・生理痛などを伴います。
血行を促す漢方薬を用いて体を温めます。
- 気血両虚
体に栄養を届ける血とエネルギーのもとである気の両方が不足している状態です。
疲れが出ると冷えが悪化しやすい特徴があり、食欲不振・めまい・不眠・倦怠感なども伴います。
治療は気血を補う漢方薬を用います。
- 腎陽虚
加齢や過労によって腎の働きが弱くなり、エネルギーを作る力が低下している状態です。
下半身の冷えが強い特徴があり、むくみ・めまい・夜間頻尿などを伴います。
腎の陽気を補う漢方薬を用います。
東洋医学における冷え症の治療は薬だけではなく、養生法の指導も合わせて行っていきます。
つらい冷え症の治療は漢方薬の得意分野!
冷え症は生活習慣が主な原因で引き起こされ、放っておくと重大な疾患につながることがあります。
西洋医学では病気ではないため治療は行われませんが、東洋医学で冷え症は解消するべき症状と考えられているため積極的に漢方薬などで治療が行われます。
つらい冷え症で漢方薬の治療を受けたい場合は体質の見極めが肝心なので、症状など話をよく聞いてくれる施設を選ぶようにしましょう。
さらに冷え症につながる体質はさまざまで根本の原因は根深いことも多いので、改善する力の強い煎じ薬を用意できる施設をおすすめします。
お近くにそのような医療施設がない場合は、私たち「漢方専門なつめ薬局」にご相談ください。
当薬局では対面のほかに電話やオンラインによるご相談も受け付けております。
どのような相談方法でも丁寧なカウンセリングを行いますのでご安心ください。
またお薬を一回分ずつパックしてお渡しするので、本格的な煎じの漢方薬を手軽に飲むことができます。
手足が冷たい、冷えがひどくて眠れないといった冷え症でお悩みがあれば、遠慮なく「漢方専門なつめ薬局」へご連絡ください。
つらい冷え症の解消に向けてお手伝いをいたします。