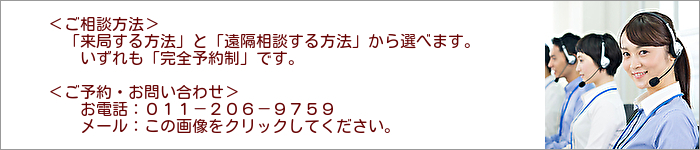東洋医学の診断ルール「八綱弁証」とは
前回まで、舌の色形を見たり、からだを触ったり、呼吸や声を聞くことなどによって、病の状態を知り診断するためのヒントを得る、「四診(ししん)」という方法についてお伝えしました。
四診によって様々な情報を得たあとは、「弁証論治(べんしょうろんち)」というルールに従って、実際の治療法を決定します。
今回は、「弁証論治」のうち、病気が今どのような状態なのかを知って病証を判断する「八綱弁証(はっこうべんしょう)」についてお伝えします。
病気を治療するときは、まず「証」をたてる
「証(しょう)」とは、東洋医学独自の考え方ですが、病の本質を示していて、治療の指針になるものです。
この「証」が決まることによって、漢方であれば処方箋を出して適切な漢方薬を処方したり、鍼灸治療であれば適切なツボを決めて鍼やお灸をすることができます。
四診によって得られた情報を元に東洋医学の原則原理に従って証を立て、実際の治療にあたるという流れです。
東洋医学というと、なんとなく曖昧な、長年のカンだけに頼っているようなイメージを持たれる方もいますが、実はそこには経験医学だからこその東洋医学の原則や原理といった緻密なルールが存在しています。
そのルールの1つが「弁証論治」であり、「八綱弁証」です。
治療方針を決める要になる弁証論治
弁証論治は、「弁証」と「論治」の2つに分けられます。
弁証とは、病気がどのような状態であるかを判断することです。
「弁証」の「弁」には判断や分析、識別という意味があり、「証」は証拠という意味があります。
つまり弁証とは、不調や病によって現れた症状を分析して、病気が発生するメカニズムである病機を検討することによって、証を定めて治療方針を決めることです。
四診によって集められたさまざまな病や不調の情報を分析して、八綱や病因、気血津液、さらに臓腑や、経絡などの基礎的な理論と照らし合わせて「証」を判断します。
そのため「八綱弁証」だけではなく、「病邪弁証」「気血弁証」「臓腑弁証」「経絡弁証」「六経弁証」「衛気営血弁証」などの弁証を駆使して多角的にからだの状態を検討して証をたてる「弁証」ができ、おのずと「論治」と呼ばれる治療方法や治療原則が決まってきます。
今回は、病をみるときに臨床で基本となる「八綱弁証」について深掘りしていきます。
八綱弁証でからだの不調や病の状況を説明できる
八綱とは、表・裏、寒・熱、虚・実、陰・陽のことを指します。
東洋医学の弁証論の基礎の一つで、四診によって得られた情報を総合的に分析して、病機や病の経過からからだの状況を説明します。
表裏について
表裏は病の深さをみます。
東洋医学では、外邪がからだの内側へ侵入したとき、その病の基になるものがどの位置にあるかによって、病態が異なっていると判断します。
- 表
からだの最も浅い部分で、皮膚や皮下の表層組織、四肢や頭、肩や背中に病が存在するときを表証といいます。
多くは風邪の初期症状で、悪寒発熱や頭痛、腰背部痛、四肢の関節痛などの症状が現れます。
- 裏
からだの最も深い部分で、腸や臓器がある場所を指し、この部位に病が存在するときを裏証といいます。
発病してから多くは一定の期間を経ている慢性的な状態で、悪熱や口渇、便秘、腹部の膨満感、腹痛などの症状が現れます。
- 半表半裏
表と裏の中間で、横隔膜に隣接する臓器類ある部分に病が存在するときを半表半裏証といいます。
病が表を通過して、まだ裏まで到達していない時に、往来寒熱や胸脇苦満、口苦、めまいなどの症状が現れます。
寒熱について
寒熱は病気の性質を区別します。
体内の陰陽の気がバランス悪く勢いづいていたり、逆に衰退していることによって起こる病の状態です。
しかし、これは体温計で図るような体温とは少し違うので注意深い観察が必要です。
- 寒
自覚的に冷えており、他覚的にも冷たく感じる状態です。
悪寒や手足の冷え、顔面蒼白、下痢、小便の色は澄んで量が多い、唇が色は淡白などの症状が現れます。
- 熱
自覚的には熱感があり、他覚的にも熱く感じる状態です。
発熱や煩躁、顔が赤くほてる、便が硬く出にくい、小便の色が濃く量は少ないなどの症状が現れます。
虚実について
虚実は病邪と正気の闘争の状態をみます。
虚と実は、病の過程で病気の原因となる邪気とからだの免疫力である正気の拮抗状態の現われです。
また、虚実は体質とも一定の関係性があります。
- 虚
虚とは、主に正気が不足している病態です。
病の後期や慢性的な疾患、誤った治療を行った場合などに多くみられます。
体質的には、骨肉がほっそりとし、胃腸が弱く、無力的な見た目が特徴です。
代表的な症状は呼吸や声の力が弱い、汗をかきやすい、筋肉に弾力がない、痛いところや不調をもんだり触ると気持ちが良いと感じます。
- 実
邪気が旺盛な状態です。
正気も比較的旺盛なので、からだの中で正邪の拮抗が激しく戦っています。
外部からの邪気である六淫による不調の初期・中期や、痰・食・水・血などの停滞による病に多くみられます。
体質的には、骨肉ががっしりしていて、胃腸が丈夫で、生命力に溢れた人に多い病証です。
呼吸や声が力強かったり、汗をあまりかかない、便秘気味、筋肉に弾力性があり、痛いところをもんだり触ったりすると気持ちが悪く、触ってほしくないと感じます。
陰陽について
病の位置や性質、勢いを陰陽の概念によって、裏・寒・虚を陰のグループ、表・熱・実を陽のグループに統括します。
病の性質に基づいて、すべての病気や不調を陰陽の概念に基づいて2つに鑑別してみることができます。
- 陰
陰とは、生体反応が沈滞し、減り弱っている病状です。
陰の属性をもつ病証を陰証といい、裏証、寒証、虚証があります。主な症状は、顔面蒼白、気分が落ち込みやすい、元気がない、言葉が少ない、手足を縮める、悪寒や冷えを訴えるなどがあります。
- 陽
陽とは、生体反応が発揚していて、強く増している病状です。
陽の属性をもつ病証を陽証といい、表証、熱証、実証があります。
主な症状は、顔色が赤くほてり感がある、活気がある、言葉が多い、手足を伸ばす、炎症や充血、発熱などがあります。
八綱弁証で実際に診断する際にとくに重要になるのは、寒熱と虚実です。
寒熱や虚実のそれぞれのカテゴリーで陰に偏っている状態なのか、陽に偏っている状態なのかをみます。
この治療原則である「弁証」ができれば、「論治」は自動的に決まるシステムになっています。
八綱弁証とは病を陰陽に分類して診断する方法
八綱弁証では病証を、表裏(病の位置から病気の進行状況みる)・寒熱(からだの冷えや熱といった性質をみる)・虚実(病の状態やからだの免疫力や体質をみる)から、陰陽の2つの概念に分類して診断し、証をたてて治療原則を見つけます。
そして、導き出された治療法によって、からだや病気の状態にあった治療をほどこします。
たとえば、人から噂を聞いて実践した健康法や治療が自分には全く効果がなかった!なんてことはないでしょうか。
それは、正しい弁証ができていないのに、治療法“だけ”を取り入れてしまっているからです。
人のからだは一人ひとり違うので、正しい診断ができていないと、自分のからだに合った良い選択をすることはできません。
良さそうな健康法や健康食品、漢方をやみくもに取り入れず、正しい知識をもってからだの養生に活かすことが大切です。