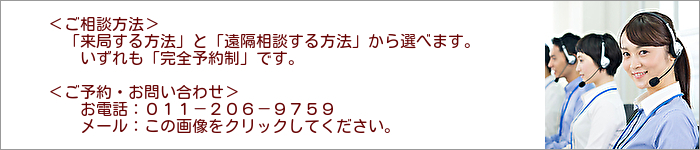【うつ病と漢方】一人ひとりの体質に応じたうつ病治療
一日中気分が落ち込んで、何をしても楽しく感じないといった精神的な症状や、眠れない・食欲がない・疲れやすいなど身体の症状にお悩みではありませんか。
このような症状が続いている場合、うつ病の可能性があります。
この記事では、うつ病について東洋医学の観点を交えて解説していきます。
うつ病とは
うつ病は日本人の15人に1人が生涯に一度はかかるといわれており、非常に身近な病気です。
うつ病には、生真面目、完璧主義、自分に厳しい、凝り性、気を遣う性質を持つ人がなりやすいといわれており、こういった性格からストレスを受けやすいと考えられています。
うつ病の症状
うつ病の症状は多岐にわたります。
精神症状では、無関心、不安・焦り・イライラ感、気分の落ち込み、意欲の低下、喜んだり楽しんだりができない、集中できない・仕事でミスが増える、飲酒量が増える、悲観的に考える、などが挙げられます。
身体症状でいえば、耳鳴り、睡眠障害(不眠・過眠)、めまい、腹痛・胃の不快感、肩こり、味覚障害、食欲不振(または過食)、動悸、頭痛などが挙げられます。
定型うつと非定型うつ
うつ病には、定型うつと非定型うつがあります。
定型うつとは、スタンダードな形のうつ病です。やる気がなくなったり、感情の起伏がみられなくなったり、食欲が減退して痩せていってしまうような症状です。
非定型うつとは、1994年にアメリカのDSM-Ⅳ(『精神障害の診断・統計マニュアル』第4版)で定義された比較的新しいうつ病です。
非定型うつは通常のうつ病と逆の症状が出るタイプとされています。
例えば、気分の変動が激しく、夕方から夜にかけて憂鬱になりやすく、過食傾向になることが多いことが特徴とされています。
非定型うつ病は、20~30代の女性に多く見られ、パーソナリティ障害や強迫性障害、不安障害を併発することもしばしば認められます。
東洋医学と鬱
東洋医学には、「心身一如」という言葉があります。
これは、「心と体は別物ではなく、お互いに影響を与え合っている」という考え方です。
この、心身一如の考えが根底にある東洋医学では、気分の落ち込みなどメンタルの症状が中心のうつ病も、身体全体の機能を回復させることで治癒に導くことを目指します。
主症状である気分の落ち込みは、漢方では「気」の異常と考えます。
「気」は人の身体を動かすエネルギーの源です。
「気」の異常|状態による分類
東洋医学では、異常な気の状態に応じて呼び方があります。以下で簡単に説明します。
「気虚」は、気が不足している状態です。
この状態になると、疲れやすい、やる気が出ない、だるい、食欲がない、めまいがするなどの症状が出てきます。
「気滞」は、気がうまく流れない状態です。
イライラする、不安になる、気分が落ち込む、のどに違和感があるなど症状が起こりやすく、お腹にガスが溜まることや睡眠に問題が出ることもあります。
「気逆」は、ストレスや怒りなどで気が逆行してしまっている状態です。
本来、気は上半身から下半身へと流れるものですが、逆行すると頭の方に流れてしまいます。
そのため、怒りっぽくなったり、のぼせや頭痛などの症状が起こったりします。
「気血両虚」とは、気の不足とともに、全身に栄養や酸素を運ぶ役割をする血も不足している状態です。
気虚による症状に加えて、動悸や不眠など血虚の症状も現れます。
漢方薬によるうつ病治療
身体の中ではさまざまな要因が複雑に絡まりあい、うつ病の症状として表れます。
症状の大元の原因を探り、原因に応じて気血水の過不足や流れを整える働きをする漢方薬を選ぶことが大切です。
主症状の治療のほかにも、漢方薬は抗うつ剤で取りきれなった自律神経症状(やる気が出ない、頭痛、肩こり、便秘など)の改善に活用できます。
また、抗うつ剤の中には、便秘や口の渇き、胃腸症状、めまい、ふらつき、尿が出にくいなどの副作用が出てしまう薬があります。
基本的に副作用が強い場合は抗うつ剤が減量されますが、漢方薬で副作用の症状を緩和させるケースもあります。
漢方薬治療における注意点
西洋医学の一般的な病院で処方される漢方薬は、症状に対して薬を処方するので、「鬱」と診断された方には、だれでも同じような漢方薬が処方されます。
けれども、東洋医学で漢方薬を処方する場合は症状だけでなく、その方の体質や身体全体の要素をみます。
そのため、同じような症状であっても人によって処方される漢方薬は異なります。
漢方薬を処方してもらう際には、しっかりと全身の状態を見極めてくれる漢方専門のクリニックや薬局を選ぶと良いです。
うつ症状が出ている根本的な原因を探るためには、生活習慣も含めてしっかりと話を聞いてくれる薬局かどうかがポイントです。