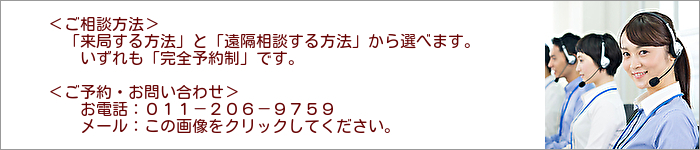これまで2回にわたって四診という東洋医学独自の診断方法についてお伝えしてきました。
今回はその中で、実際の漢方での処方や鍼灸治療の施術方針を決めるときに重要視する、また比較的分かりやすい『舌診(ぜっしん)』について深掘りしていきます。
ぜひ手元に鏡を用意し、ご自身やご家族の舌を見ながら読み進めて、お悩みや不調の原因を探すヒントにしてください。
健康的な舌を知ることから舌診をはじめる
舌診は望診(ぼうしん)のひとつで、舌を観察する診断方法です。
舌診では、舌の形や舌質の色と性質、舌の苔の色や厚さに注目します。
舌体(ぜったい)とは舌自体のこと、舌質(ぜっしつ)とは舌の肌やお肉などの組織のこと、舌苔(ぜったい)とは舌の上に付着している苔状のもののことをいいます。
舌の変化は客観的に身体の気血の虚実、病邪の性質、病位の深さ、病気の進展状況を反映しています。
虚実、つまり五臓のエネルギーが不足しているのか旺盛なのかという判断には、舌体の形と舌質の色をみます。
寒熱などの病邪の性質や病位の深さ、消化吸収に関わる胃気の状態をみるときは、舌苔の観察が重要です。
- 健康的な舌の形
腫れて大きくなっていたり縮こまっていたり、こわばりや歪みなどがなく、舌の表面のひび割れ、舌の縁に歯の痕が残っているなど、舌の形を損なう変化をしていない状態が健康的で正常な舌の形です。
- 健康的な舌質の色
淡紅色が正しい舌の色です。
薄紅色、つまりあわいピンク色であれば、気血が適切にめぐっている状態です。
- 健康的な舌苔色と性質
適度に潤いがあり、舌の中心に白い苔がうっすらとある状態です。
不調のあるときや未病のときの病的な舌はどんな状態?
舌の形と色は、五臓六腑のエネルギーである正気の盛衰の状態をみることができます。
そのため、重い病気の場合は予後を判断するのにとても重要な役割をもちます。
また、舌苔では苔の色と厚さ、苔質を観察します。
病邪の性質(寒熱)は舌苔の色と深い関りがあり、舌苔の厚さは病邪の程度や病気の進行状況を判断するのに役立ちます。
舌のかたち
- 胖舌(はんぜつ):舌体がボテッとして腫れ感があり、大きいもの
身体を温める力がないために冷える陽虚や、炎症や発熱性の疾患のある状態です。
- 痩舌(そうぜつ):舌体に力がなく、薄く小さいもの
気血両虚や陰虚の状態です。
気血両虚は身体の気と血が不足しているため、全身の機能や活動が低下します。
陰虚とは、身体を潤したり冷却水のような役割をもつ水が不足するためにほてりやすくなるなどの症状が現れる病態です。
- 裂紋舌(れつもんぜつ):舌の表面にタテに亀裂があるもの
陰虚や血虚の状態です。
血虚とは、文字通り血が足りていない状態で、全身に栄養がいきわたらず、貧血や新陳代謝の低下、精神の安定を図ることができなくなります。
- 歯痕舌(しこんぜつ):舌体の淵に歯の跡がギザギザに残っているもの
胖舌と合わせて現れることが多く、気虚や脾虚の状態です。
身体のエネルギーが足りないことによって舌にたるみ感があったり、脾胃の働きが低下することによって津液の代謝低下が起こり舌がむくんだりします。
余分な水分がたまって大きくなった舌に歯の痕がつきます。
- 芒刺舌(ぼうしぜつ):舌の表面にトゲ状の隆起があるもの。
熱邪、臓腑に熱がある状態です。
炎症など発熱性の疾病があり、とくに舌先にトゲトゲがある場合は心、舌体の真ん中あたりは脾胃、両サイドの場合は肝胆に熱がこもっているとみることができます。
- 硬舌(こうぜつ):舌が緊張したように固く、運動が滑らかではないもの
東洋医学で中風とよばれる脳卒中の前兆や、高熱、痰濁という身体に余分な水分が溜まっている状態です。
- 軟舌(なんぜつ):舌体が弛緩して、力がないもの
気血両虚、陰虚などの状態です。
気血も陰液と呼ばれる津液も、身体を栄養したり円滑に身体を動かすためのエネルギーとなるものです。
これらが不足すると、力がなくなり、正しく運動することができなくなります。
- 顫動舌(せんどうぜつ):舌を出すと震えて止まらないもの
気血両虚、陽虚などの状態です。
神経質だったり、緊張から震えてしまったりすることもありますが、気血両虚、陽虚が原因で震える場合は、止めたくても止まらない状態となります。
- 歪斜舌(わいしゃぜつ):舌を出したときに自然と左か右のどちらかに歪むもの
脳卒中である中風、あるいはその前兆がある状態です。
まっすぐ出したつもりでも、左右のどちらかに歪んで出ている場合は、脳血管系の疾病に注意する必要があります。
舌質の色
- 淡紅色(たんこうしょく):正常な血色をしているもの
正常、あるいは軽い熱傷がある状態です。
- 淡舌(たんぜつ):≪浅紅舌≫正常な舌の色より赤くなく、淡白な淡い色をしているもの
陽虚、血虚、寒証がある状態です。
身体をあたためる陽気や血が不足しているために、通常より白っぽくなります。
- 紅舌(こうぜつ):≪鮮紅舌≫正常な舌の色より濃い赤い色をしているもの
実熱、陰虚による虚熱がある状態です。
淡舌とは逆の様相を示しています。
赤味が強い場合は身体に熱がこもっています。
- 絳舌(こうぜつ):≪深紅舌≫舌の色が深い紅色であるもの
熱性けいれんのような状態を指す熱極や、陰虚による陰火がある状態です。
陰火とは、なにかしらの原因によって元気を損傷したり、陰陽のバランスが崩れることによって発生する不自然な火のことを指します。
- 紫舌(しぜつ):≪青紫舌≫舌色が青紫色であるもの
血瘀、熱毒、寒証がある状態です。
血の巡りが悪い病態を血瘀、陽気の衰退や寒邪を受けて冷えの症状が現れることを寒証、熱が体内にこもり、はれたり化膿するような病因を熱毒といいます。
舌の苔
舌苔の色について
- 白苔(はくたい):一般的な苔の色で、白色の苔です
正常な苔の状態です。
まれに表証、寒証があります。
表証とは病気が身体の表面上にある状態で、病気の進行とともに裏である身体の中に入っていきます。
風邪の初期に治療すれば治りが早いのは、表面上に病気があるからです。
- 黄苔(おうたい):黄色い苔です
常にカレーを食べた後のように苔が染まっている、熱証、裏証がある状態です。
裏証とは、時間の経過とともに次第に病気が身体の中に入ってしまっている状態です。
すぐ治さなかった風邪で咳がしつこく残ってしまうのは、病邪が裏に入ってしまっているからです。
- 灰苔(かいたい):薄い黒色で、浅黒い灰色の苔です
裏熱証、寒湿証がある状態です。
外邪が身体の裏である深部に入り込み熱を伴っている病証です。
寒湿証では、身体のなかで冷えて停滞した水分が、巡りを悪くしています。
灰苔が濃くなると黒苔になります。
- 黒苔(こくたい):黒色、または焦げたような煤けた色の苔です
病状が重くなると、灰色から黒色の苔になります。
裏証での熱極、寒盛がある状態です。
寒盛とは、寒証が特に強い様子のことを指します。
熱性けいれんなど高熱になったり、著しい冷えなど、寒熱のバランスが激しく乱れています。
舌苔の厚さと苔質について
- 薄苔(はくたい):苔が少なく、透けて肌色の舌体が見えているもの
正常な状態、あるいは表証や虚証であっても邪気が弱く、体への不調は大きく及ばない状態です。
- 厚苔(こうたい):苔が厚く、舌の本体が苔で見えないもの
裏証や実証、あるいは邪気が強く、食べ過ぎたときになる苔の状態です。
- 潤苔(じゅんたい):苔に潤いがあり、ベタベタとした湿り気を帯びているもの
正常(津液の未損失)、または湿邪がある状態です。
乾燥していても良くないのですが湿り気を帯びている場合、湿邪があるとみます。
- 燥苔(そうたい):苔が乾燥しているもの
津液の損傷や燥邪がある状態です。
乾いているということは、身体にとって必要な水分である津液が足りていないとみます。
- 滑苔(かつたい):苔の水分過多状態で、透明な膜のようなものに舌が覆われているもの
水湿の停滞がある状態です。
身体の湿度が高いために、水分でしっとりとしています。
- 膩苔(じたい):苔が舌体からはがれにくく、ねっとりとしているもの
痰飲、湿濁がある状態です。
苔が油を帯びたようなベタベタとした汚い見た目になっています。
身体に余分な水分が溜まっています。
- 腐舌(ふたい):苔が舌の上でおから状のようになり、舌体から剥がれやすいもの
食積という、食べ過ぎて痰濁のような身体に余分なものがある状態です。
ベッタリとはしていますが、膩苔と違いぬぐったりすると簡単に苔が剥がれ落ちることが特徴です。
- 剥落苔(はくらくたい):苔の一部、あるいはすべてが剥がれ落ちているもの
気陰両虚の状態です。
気や滋潤する津液が足りていないので、栄養不足や免疫力が低下しているような病症があらわれます。
苔がうすい状態からどんどん厚く変化する過程は、病邪と呼ばれる病因になるものが身体の表面から中に入り込み、病状が進行していることをあらわします。
逆に苔の厚い状態から薄く変化することは、病邪が中から外へ出てきて病状が好転していると判断できます。
舌診がわかると自分を診察することができるようになる
舌をみることで体調やその原因が分かるようになると、「なんとなく調子が悪いな」と感じたとき、不必要に身体を心配することなく適切な養生をすることができます。
また、日々舌を観察し今の自分の体質や状態を知ることで、快く過ごすための様々なヒントが得られます。
例えば舌が歪んでいた場合、歪斜舌は脳卒中と関係するので、遺伝的にご親族に脳血管系の病気を患った人がいる方は、健康診断の時にしっかり検査しようかなと意識し、早期発見や予防に努めることができます。
伝統的な診断方法である四診を用いることで、適切な養生や必要な治療を受けることが出来るようになるのです。
ただし、歯ブラシで苔が剝がれてしまうと正しい舌診ができません。
舌を歯ブラシ等で磨いている方は舌診をする際は注意が必要です。