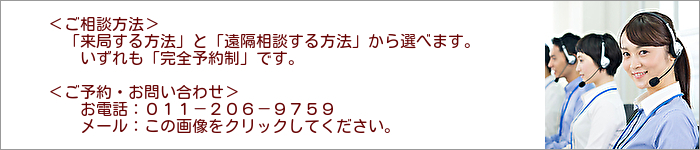漢方医学の大原則:気血津液と精について
中医学における気血津液の存在
中医学を語る上で、絶対に外すことができないものの1つに『気・血・津液(しんえき)』の存在があります。
この3つの物質は、私たちが生命活動を行う上でなくてはならない源です。
またこれらは、『精』というエネルギーの元から、五臓や六腑の働きによって生成・代謝されています。
今回はこの気血津液とその元となる精について、それぞれお話していきます。
気血津液の元となる2つの『精』
気血津液の元となる『精』は、2種類あります。
- 先天の精
両親から受け継いだ、生まれもったエネルギーのこと。
心身をつくり成長させていく元となります。
生まれてからは五臓の腎に蔵され、気の1つである原気となって発育や成熟といった基本的な生命活動に使われ、後天の精によって常に補充されます。
- 後天の精
食べ物や飲み物から得ることができるエネルギーのこと。
臓腑の脾胃によって作られ、先天の精を補給し生命活動を支える基盤になります。
気の営気、衛気、宗気や津液、血の元となります。
若い方や生活習慣が整っている方は、精が充実していて、五臓や筋肉、骨格も丈夫で、気力に満ち溢れていて、活動的で免疫力も高く、病気になりにくいです。
また、もし不調や病気があらわれても早い回復を見込むことができます。
精が充実していることは、わたしたちにとってとても重要なことが分かります。
目に見ることができない『気』について
一言で『気』といっても、その働きは色々あります。
- 原気(げんき):元気
先天の精が変化生成したもので、食欲や性欲など生きようとする欲求をもたらすような、生命活動の原動力となるものです。
後天の精によって補給され、ヘソ下の丹田(たんでん)という場所に集まり、経絡を介して全身を巡り、臓腑、器官、組織に活力を与えます。
- 宗気(そうき)
後天の精と呼吸によって得た天の陽気とよばれる自然界のエネルギーが肺で交わって、膻中(だんちゅう)に集まる気です。
五臓の心を規則正しく拍動させ、肺の呼吸などの働きを支えています。
- 営気(えいき):栄気
後天の精から得られる陰の性質をもつ気です。
津液を血に変化させ、血とともに身体の内側を1日に50回巡り、臓腑や手足など各器官を営養し活動させます。
- 衛気(えき)
後天の精から得られる陽の性質をもつ気です。
衛気は、日中に体表部を25回、夜間に体内を25回ずつ素早く巡り、体表の温度調節に関わり、腠理(そうり)という皮膚と筋肉が交わるところの収縮と弛緩を行っています。
体表近くで活動し、不調の原因となる外邪(がいじゃ)から防御する働きを持ちます。
- その他の気
・真気:正気
先天の精と後天の精からなるもので、病気に対する防衛能力と環境に対する調整能力のことです。
病気の発生や進行に関わっています。
・臓気(ぞうき)
五臓に収まり、それぞれの活動を支えています。
中でも胃を働かせる、もしくは胃の働きによって得られた後天の気のことを胃気(いき)といいます。
胃気の有無は病気後の心身の回復に大きな影響をおよぼすため、重要とされています。
・経気(けいき)
気血の通り道である経絡を巡り、その活動を支えています。
現代医学とは少し違う東洋医学の『血』の働きについて
東洋医学でいう『血(けつ)』は、字の如くそのまま私たちがよく知っている赤い血(ち)のことです。
ただしその働きは、近代医学とは若干異なっています。
中医学は顕微鏡でみることのできない時代からある医学なので、血小板や白血球などの見地とは別の角度から血を捉えています。
血は脾胃からもたらされる後天の精から作られます。
そしてその素材は、津液と営気からできています。
営気とともに身体を巡り、四肢や五臓六腑を潤し、その働きを支えます。
夜、布団に入り横になると血を貯蔵する働きをもつ肝にしまわれ、目が覚め活動すると必要に応じて全身を巡り、身体円滑に動かします。
また、血は精神や意識的な活動の基本物質となります。
血が充実すると気も充実するため精神が安定します。
物事に対する反応も素早く行うことができ、身体も俊敏に動かすことができます。
身体の中を流れる血液以外のすべての体液:『津液』について
津液とは、体内の水分を総称したもののことをいいます。
日本の漢方ではこれを『水』という場合もありますが、中医学では『津液』と呼びます。
『津』と『液』、それぞれに意味と役割があります。
- 津(しん)
陽の性質をもった水分のことをさします。
サラサラとして粘りけがなく、主に体表部を潤し体温調整にも関わります。
また、汗や尿となって体外に排出されます。
- 液
陰の性質をもった水分のことをさします。
粘りけがあり、体内をゆっくり流れています。
骨や骨の中の髄まで潤し、目や鼻、口などの粘膜や皮膚に潤いを与えます。
津液の源は私たちが口から摂取した食べ物や飲み物です。
飲食物が胃や腸にはいって津液が作られます。
気血津液を充実させるために大切なこと
気・血・津液は精が変化しつくられたものです。
両親より受け継いだ先天の精、飲食物から得た後天の精というエネルギーの源からまず原気がつくられ、さらに呼吸や飲食物をもとに、宗気、営気、衛気、血、津液がつくられます。
この気血津液が五臓の働きによってつくられ、またその働き自体を支えています。
気血津液は精が充実していることによって、充分に作られ身体の中で巡り働いています。
この精が不足してしまうと、気血津液が足りなくなり五臓や身体を満足に働かせることができなくなってしまいます。
同じ精でも、前述した通り先天の精はあとから増やすことはできませんが、後天の精は違います。
質の良い食べ物や飲み物といった口から摂取するものや、睡眠などの生活習慣によって補うことができます。
日々の養生がいかに大切か分かります。